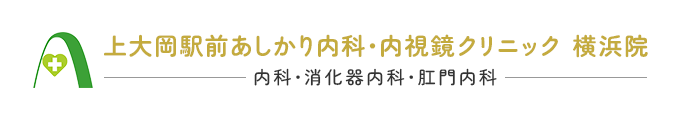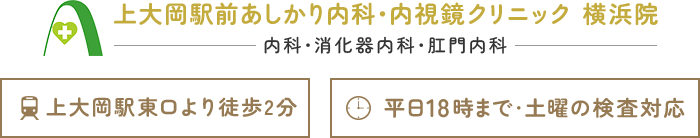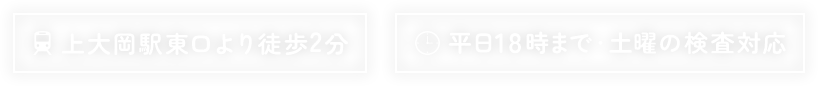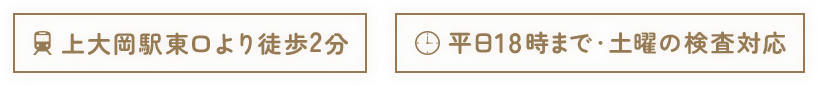消化器内視鏡専門医・
消化器病専門医である
院長による診療
土曜の胃カメラ・大腸カメラ対応
仕事や子育てでお忙しい方でも安心して検査を受けられるよう、土曜日にも胃カメラ・大腸カメラ検査を行っています。
鎮静剤を使用して痛くない・
苦しくない胃カメラ・大腸カメラ
鎮静剤を使用することで、リラックスした状態で検査を受けていただけます。患者様の苦痛や不快感を最小限に抑えた検査を心がけております。
日帰り大腸ポリープ切除対応
検査中に大腸ポリープなどの病変を見つけた場合、その場で切除手術を行うことが可能です。大腸ポリープ切除は日帰り手術で対応しております。
胃・大腸カメラ同日検査も対応
同日に胃カメラ検査・大腸カメラ検査を受けていただくことができます。同日に受けることで事前の食事制限が1度で済むほか、検査後の制限も1度で済みます。仕事などで忙しい方や何度も来院されるのが難しい方にお勧めしております。
当日胃カメラ検査に対応
初診日当日でも、検査の空き枠や食事時間などの条件が揃った場合、即日胃カメラ検査を受けることが可能です。
検査終了後、
そのままリカバリールームで
お休み頂けます
リカバリールームを完備しております。プライバシーに十分配慮したスペースで、安静にお過ごしいただけます。
検査終了後は、寝たままリカバリールームに移動が可能です。
二酸化炭素による
おなかの張りを軽減
大腸を膨らませる送気には炭酸ガスを用いております。通常では、大量の空気を送気することで不快感や強い腹部膨満感が起こりますが、炭酸ガスを用いることで検査後の膨満感を解消することができます。
院内下剤半個室4室・
トイレ2室完備
院内下剤服用半個室が4部屋、トイレ2室を完備しております。ご自宅での下剤の服用に不安がある方はお気軽にご相談ください。
内視鏡検査室2部屋・
リカバリーベッド5台完備
内視鏡検査室2部屋、リカバリーベッド5台を完備しております。検査終了後は、リカバリールームまで横になったまま移動できます。
最新の内視鏡設備を導入
最新の内視鏡設備を導入しています。最大拡大倍率135倍の光学ズームを搭載し、対象病変を高倍率で拡大観察を行うことができます。また、高感度CMOSイメージセンサーにより、ノイズが少なくハイビジョンを上回る高画質で観察することができ、さらに質の高い検査を行うことができます。
消化器内科
 消化器内科では、食道・胃・小腸・十二指腸・大腸など、口から肛門までの消化管と、肝臓・胆嚢・膵臓などの症状や疾患を幅広く診療しています。消化器疾患で起こる主な症状は、腹痛、下痢、便秘、下血、血便、吐き気、嘔吐、食欲不振、腹部膨満感などが挙げられます。
消化器内科では、食道・胃・小腸・十二指腸・大腸など、口から肛門までの消化管と、肝臓・胆嚢・膵臓などの症状や疾患を幅広く診療しています。消化器疾患で起こる主な症状は、腹痛、下痢、便秘、下血、血便、吐き気、嘔吐、食欲不振、腹部膨満感などが挙げられます。
これらの症状が起こる原因を特定するために、問診を行い、必要に応じて血液検査、胃・大腸カメラ検査、超音波検査などを実施します。消化器症状には、胃がんや大腸がんなど重篤な疾患が隠れていることもあるため、注意が必要です。気になる症状がある場合は、お早めに当院までご相談ください。
消化器の症状と疾患
当院の消化器内科では、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓における症状や疾患について、幅広く専門的に診療しております。
下記の症状がある方は
ご相談ください
お腹の不調などよく起こる些細な症状でも、何らかの疾患の症状として現れることもあります。
気になる症状がありましたら、お気軽に当院までご相談ください。
消化器の主な病気
逆流性食道炎
 胃液や胃の内容物が胃から食道に逆流してしまうことで、食道粘膜が炎症を起こしてしまう状態が、逆流性食道炎です。酸っぱいと感じる呑酸や喉がヒリヒリしたり、胸焼けが起きたりします。慢性的な咳の原因になることもあります。過度の飲酒習慣や食生活の乱れ、肥満、加齢、食道裂孔ヘルニアなどが原因とされます。胃酸分泌の増加や胃酸逆流防御機能の低下などが原因で起こります。逆流性食道炎の頻度は増えており、注目されている疾患です。検査をすると食道がんが見つかることもあり、上記の症状がある方は一度、胃カメラで食道を検査することをお勧めします。治療にはPPI/PCABやH2ブロッカーなど胃酸の分泌を抑制するお薬で症状を緩和することができるので、消化器内科専門医に相談すると良いでしょう。
胃液や胃の内容物が胃から食道に逆流してしまうことで、食道粘膜が炎症を起こしてしまう状態が、逆流性食道炎です。酸っぱいと感じる呑酸や喉がヒリヒリしたり、胸焼けが起きたりします。慢性的な咳の原因になることもあります。過度の飲酒習慣や食生活の乱れ、肥満、加齢、食道裂孔ヘルニアなどが原因とされます。胃酸分泌の増加や胃酸逆流防御機能の低下などが原因で起こります。逆流性食道炎の頻度は増えており、注目されている疾患です。検査をすると食道がんが見つかることもあり、上記の症状がある方は一度、胃カメラで食道を検査することをお勧めします。治療にはPPI/PCABやH2ブロッカーなど胃酸の分泌を抑制するお薬で症状を緩和することができるので、消化器内科専門医に相談すると良いでしょう。
好酸球性食道炎
白血球の中でアレルギー反応に関与する好酸球という細胞が、食道にたくさん集まり、慢性的な炎症を生じさせる疾患です。炎症が持続することによって食道の動きが悪くなり、食事が通りにくくなったり、ものがつかえる感じや胸やけ、胸の痛みなどの症状を生じます。さらに進行すると食道が狭くなって、食事が詰まってしまうこともあります。
我が国ではまれな病気と考えられていましたが、最近、疾患が知られるようになってきて、胃カメラで発見されるケースが増加しています。
好酸球性食道炎による症状は逆流性食道炎と似ていることもあるため、診断が難しいこともしばしばあります。好酸球が食道だけに集まった場合に好酸球性食道炎と言います。胃や腸にも好酸球による炎症が起きている場合には、好酸球性胃腸炎と呼ばれます。
ヘリコバクター・
ピロリ感染症
 ピロリ菌が胃粘膜に棲みつくことで、慢性的な炎症を起こして胃潰瘍や十二指腸潰瘍を引き起こします。胃がんやリンパ腫を発症するリスクがあるため、早期に治療することが大切です。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染は、幼少期の経口感染が原因とされており、我が国の浄水設備が整備されてからピロリ菌感染者は減少しています。しかし今でも若年層で10%前後の感染率が確認されているため、健診で指摘を受けた方は必ず胃カメラ検査を受けた方が良いです。治療は、内服薬による除菌治療を行います。除菌成功率は90%を超えており、ほとんどの方が除菌できます。
ピロリ菌が胃粘膜に棲みつくことで、慢性的な炎症を起こして胃潰瘍や十二指腸潰瘍を引き起こします。胃がんやリンパ腫を発症するリスクがあるため、早期に治療することが大切です。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染は、幼少期の経口感染が原因とされており、我が国の浄水設備が整備されてからピロリ菌感染者は減少しています。しかし今でも若年層で10%前後の感染率が確認されているため、健診で指摘を受けた方は必ず胃カメラ検査を受けた方が良いです。治療は、内服薬による除菌治療を行います。除菌成功率は90%を超えており、ほとんどの方が除菌できます。
急性胃炎
胃粘膜の炎症が急激に起こる状態を、急性胃炎と言います。急激な腹痛や吐き気、嘔吐、下痢などの症状を起こします。重症になると、下血や吐血などがみられます。主な原因は、暴飲暴食や過度の飲酒、香辛料など刺激の強い食品、薬の副作用、過度のストレス、アレルギー症状などが挙げられます。また新鮮な刺身やしめ鯖などの摂取後にアニサキスという寄生虫が胃に入り急激な胃の痛みで発症する急性胃炎もあり、その時は胃カメラでアニサキスを除去することで治療します。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
 胃粘膜や十二指腸粘膜に炎症が起こり、胃壁・十二指腸壁に深い傷ができてしまう状態です。ピロリ菌感染が主な原因とされていますが、心身のストレスや薬の副作用などが原因となることもあります。
胃粘膜や十二指腸粘膜に炎症が起こり、胃壁・十二指腸壁に深い傷ができてしまう状態です。ピロリ菌感染が主な原因とされていますが、心身のストレスや薬の副作用などが原因となることもあります。
みぞおちの痛み、背中の痛み、胸焼け、吐き気、腹部膨満感などの症状が起こります。病気が進行すると、下血や吐血などの症状が現れます。
萎縮性胃炎
慢性胃炎が進行し、胃粘膜が萎縮した状態が萎縮性胃炎です。慢性胃炎は、ピロリ菌感染によって起こるため、ピロリ菌に感染したら早めに除菌治療することをお勧めしております。ピロリ菌除菌治療は、将来の胃がん発症リスクを大幅に低下できます。なお、除菌治療を行った後も定期的に胃カメラ検査を受けることが大切です。
好酸球性胃腸炎
消化管に炎症が起きて様々な症状を引き起こす病気で、様々な年齢層で発症する可能性があります。吐き気、嘔吐、腹痛、腹部膨満感、血便などの不快な症状が1カ月以上続きます。 食欲不振や体重減少などに発展することもあります。
診断するには胃カメラ、大腸カメラなど内視鏡検査をおこない、消化管粘膜の組織を採取し、顕微鏡で好酸球という細胞がたくさん集積していることを確認することで診断できます。しかし、内視鏡では正常な粘膜にみえることもしばしばあるため、問診の段階で疑わなければ診断できず、消化器専門医や内視鏡専門医であっても丁寧な問診と経験がなければ診断することは困難です。
経過観察で治らない場合は、内服治療で消化管の症状を抑えます。標準治療はステロイド内服ですが、ステロイドには副作用もあるため気を付けるべきことがたくさんあるので専門医にご相談ください。
便秘症
 便秘はよく起こる症状のため、放置してしまう人も多いですが、重篤な疾患の症状として現れることもあるため注意が必要です。特に大腸がんの進行によって便秘が引き起こされている場合は気づきにくいことがあるため注意しなくてはいけません。また排便時にいきんでしまう癖がある方は心疾患のリスクが高いことがわかっており、スムーズに便を排泄させるために便秘薬を使用することが推奨されています。便秘症の原因は多岐に渡るため、便秘にお悩みの方は早めに医療機関を受診することをお勧めしております。また、便秘症状に加えて、発熱や吐き気、強い腹痛、血便などの症状がある場合は、速やかに受診してください。
便秘はよく起こる症状のため、放置してしまう人も多いですが、重篤な疾患の症状として現れることもあるため注意が必要です。特に大腸がんの進行によって便秘が引き起こされている場合は気づきにくいことがあるため注意しなくてはいけません。また排便時にいきんでしまう癖がある方は心疾患のリスクが高いことがわかっており、スムーズに便を排泄させるために便秘薬を使用することが推奨されています。便秘症の原因は多岐に渡るため、便秘にお悩みの方は早めに医療機関を受診することをお勧めしております。また、便秘症状に加えて、発熱や吐き気、強い腹痛、血便などの症状がある場合は、速やかに受診してください。
便秘症の治療はガイドラインに従っておこなう必要があります。市販薬や通販のお茶、サプリメントには好ましくない成分が含まれることが多く、また高齢者では酸化マグネシウムを漫然と内服することは危険なこともあります。便秘症は軽く考えられがちですが、間違った知識や治療法がよく見られますので、一度は専門医のお話を聞くとよいでしょう。
感染性腸炎
細菌やウイルス、寄生虫などによる感染によって起こる腸炎を、感染性腸炎と言います。細菌性では、サルモネラ・カンピロバクター・腸炎ビブリオ・O-157(腸管出血性大腸菌)など、ウイルス性ではノロウイルス・アデノウイルス・ロタウイルス・エンテロウイルスなどによって腸炎を起こします。主な症状は、急激な下痢、腹痛、発熱、血便、吐き気、嘔吐、下血などがみられます。
過敏性腸症候群
 下痢や便秘を繰り返す疾患ですが、それが数か月以上続くため、日常生活に支障を及ぼすことがあります。検査を行っても器質的異常がみられないため、完治できる治療法がなく、厚生労働省に難病指定されている疾患です。特定できる原因は不明ですが、心身のストレスなどが関与しているとされています。
下痢や便秘を繰り返す疾患ですが、それが数か月以上続くため、日常生活に支障を及ぼすことがあります。検査を行っても器質的異常がみられないため、完治できる治療法がなく、厚生労働省に難病指定されている疾患です。特定できる原因は不明ですが、心身のストレスなどが関与しているとされています。
クローン病
小腸や大腸など消化管全域の粘膜に炎症が起こります。明確な原因が分かっていません。クローン病は、炎症性腸疾患の1つで難病指定されています。主な症状は、腹痛、下痢、血便、発熱、栄養障害、体重減少、痔ろうなどが現れます。慢性的な炎症や浮腫、潰瘍ができます。
潰瘍性大腸炎
大腸粘膜に炎症やびらん、潰瘍ができます。はっきりとした原因が分からず、難病指定されています。
主な症状は、腹痛、下痢、血便、便が出ないなどが起こります。病気が進行すると、発熱、貧血、体重減少などの症状がみられます。
肝機能障害
様々な原因によって肝細胞に炎症が起こり、次第に肝細胞が侵されてしまう状態が肝機能障害です。健診などの血液検査で異常と指摘されるのは、肝細胞の酵素(ALT・AST)が血中に漏れるためです。治療せずに放置すると、肝硬変や肝がんなどに進行してしまうため注意が必要です。
肝硬変
脂肪肝やアルコール性肝障害、肝炎ウイルスなどによって、線維組織が肝臓に増えて次第に硬くなってしまう状態が肝硬変です。症状が現れる時期と治まる時期を繰り返し、症状がある場合は黄疸や浮腫、腹水、吐血、肝性脳症などを併発します。
胆石(胆のう結石症)
胆のう内に結石ができる状態を、胆石と呼びます。主な症状として、肋骨下に強烈な痛みが起こります。みぞおちや右の肋骨の下、右肩、背中に痛みが現れるほか、黄疸の症状が現れます。食生活の欧米化や高齢化などが原因とされています。無症状の状態で、検診で発見されることもよくあります。
急性膵炎
 膵臓に急激な炎症が起こり、膵液の消化酵素によって膵臓自体が消化されてしまう状態が急性膵炎です。主に、みぞおちや上腹部、背中に強い痛みが生じるほか、発熱や嘔吐、黄疸の症状が現れます。過度の飲酒や胆石症によって引き起こされると言われています。
膵臓に急激な炎症が起こり、膵液の消化酵素によって膵臓自体が消化されてしまう状態が急性膵炎です。主に、みぞおちや上腹部、背中に強い痛みが生じるほか、発熱や嘔吐、黄疸の症状が現れます。過度の飲酒や胆石症によって引き起こされると言われています。
食道がん
食道がんの初期段階ではほとんど症状がみられません。病気の進行に伴って、飲み込む際のつかえ感、胸がしみる感じ、胸の痛みなどの症状が現れます。習慣的に飲酒や喫煙をする方、バレット食道と指摘された方は注意が必要です。早期発見のためにも、定期的に胃カメラ検査を受けることが大切です。
胃がん
胃炎や胃粘膜の萎縮によって胃がんを引き起こします。主な原因は、ピロリ菌感染とされ、その他では過剰な塩分摂取や喫煙、食生活の乱れなどが挙げられます。胃がんは初期症状がほとんど無いため、早期発見のためには胃カメラ検査を定期的に受けることをお勧めしております。
大腸がん
大腸がんは、大腸粘膜の炎症や大腸ポリープが進行して引き起こされます。食生活の欧米化や高齢化など、様々な要因が考えられます。自覚症状が乏しいまま病気が進行してしまうため、定期的に大腸カメラ検査を受けることが大切です。
また、大腸ポリープができた場合は、大腸ポリープ切除を受けることで将来の大腸がんの発症リスクを抑えることができます。
膵臓がん
膵臓がんも自覚できる症状がないため、早期発見が困難な疾患とされています。初期症状としては、腹部の違和感や食欲不振などが現れ、病気の進行に伴って腹痛や腰痛、背部痛、胃部不快感、黄疸などの症状が起こります。
考えられる原因としては、過度の喫煙や糖尿病、慢性膵炎、膵嚢胞、家族歴などが挙げられます。早期発見のために、血液検査や腹部CT検査などを受けられることをお勧めします。