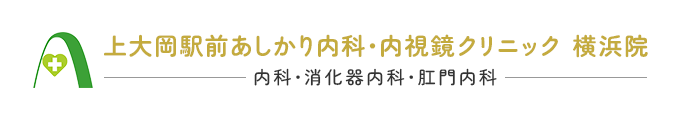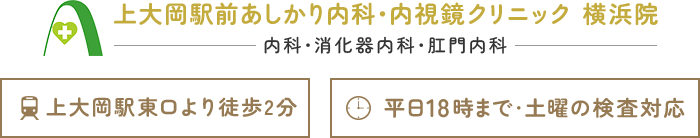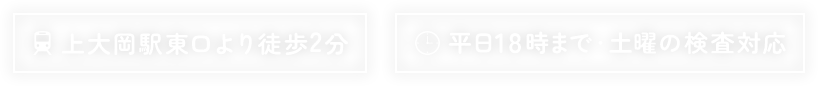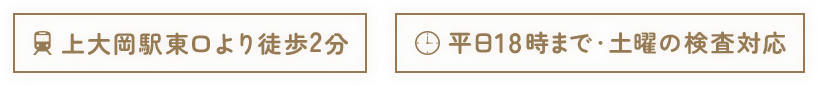内科について
 当院の内科では、腹痛、便秘、下痢、嘔吐、吐き気、胸痛などのほか、生活習慣病である高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症など幅広く診療しております。
当院の内科では、腹痛、便秘、下痢、嘔吐、吐き気、胸痛などのほか、生活習慣病である高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症など幅広く診療しております。
体調が優れず具合が悪いけれど、どの診療科を受診すればいいのか分からない場合も、まずは内科を受診してください。
※当院では、初診での発熱診察対応を行っておりません。予めご了承ください。
このような症状・疾患が
ありましたら
ご相談ください
- 吐き気
- 嘔吐
- 便秘
- 下痢
- 喉の渇き
- 倦怠感
- 疲労感・疲れやすい
- 気力がない
- 胸が痛い、苦しい
- イライラする
- 眠れない・夜間起きてしまう
- 食欲がない・体重減少
よくある疾患
 生活習慣の乱れから発症する慢性疾患を生活習慣病と言います。具体的に、暴飲暴食、過度の飲酒・喫煙習慣、運動不足、ストレスなどが原因で、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝などを発症します。乱れた生活習慣によって、血管が次第に詰まりやすくなり動脈硬化が進んでしまいます。高血圧から心不全や心筋梗塞などの心疾患、脳溢血や脳梗塞などの脳血管疾患を招いてしまうこともあります。糖尿病や脂肪肝は、がんの発症との関連性も指摘されており、注意が必要です。
生活習慣の乱れから発症する慢性疾患を生活習慣病と言います。具体的に、暴飲暴食、過度の飲酒・喫煙習慣、運動不足、ストレスなどが原因で、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝などを発症します。乱れた生活習慣によって、血管が次第に詰まりやすくなり動脈硬化が進んでしまいます。高血圧から心不全や心筋梗塞などの心疾患、脳溢血や脳梗塞などの脳血管疾患を招いてしまうこともあります。糖尿病や脂肪肝は、がんの発症との関連性も指摘されており、注意が必要です。
また、近年増加の一途を辿る花粉症など、アレルギー疾患もよくみられます。当院では、上記に挙げた疾患をはじめとする幅広い疾患に対して、丁寧な診療を心がけております。健康診断で異常を指摘された方や、親兄弟などの親戚に生活習慣病の既往がある方は、お気軽に当院までご相談ください。
糖尿病
血液中のブドウ糖が過剰になり、血糖値が通常よりも高い状態が続くと糖尿病になります。高血糖の原因は、インスリンの機能低下や分泌量低下などインスリン分泌が不十分な場合と、インスリンは十分にでているけど十分に効果が発揮できないインスリン抵抗性が悪化する場合があり、血糖値が正常に戻らなくなります。糖尿病の初期症状はほとんどありませんが、血糖値が上昇すると異常に喉が渇きます。尿量が増えるほか、全身の倦怠感が起こったり、体重減少がみられたりもします。このような症状が現れたら糖尿病の可能性が考えられます。糖尿病を治療せずに放置すると、網膜症(視力が低下する)、腎症(腎臓の機能が衰え、最終的に透析になる)、神経症(手足の感覚異常が出てくる)といった合併症を起こしたり、心疾患、脳血管疾患、がんなど大きな病気に発展したりします。生活習慣を見直し、場合によってはお薬を飲むことで正常な状態に近づけることがとても大切です。
脂質異常症
血中のコレステロール値や中性脂肪値などが異常に高い状態が脂質異常症です。脂質異常症は自覚できる症状がないまま病気が進行します。その結果、動脈硬化が進み、血管が閉塞してしまい心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしてしまいます。このため、目立つ症状がなくても、定期的に健診などで検査を受けることが非常に大切になります。
脂質異常症は、脂質の高い食事や過度の飲酒・喫煙習慣、運動不足、肥満など生活習慣の乱れによって発症してしまいます。このため、規則正しい生活とカロリー制限など生活習慣の改善を行いながら治療を進めます。また女性の方は、閉経すると女性ホルモンの一つであるエストロゲンが減少しコレステロールが上昇してくることもあります。大切なのは、頸動脈エコーなどで動脈硬化の程度やプラークの有無を評価しておくことです。他の生活習慣病の有無や動脈硬化の程度を総合的に評価してお薬を飲む必要があるか医師にきちんと判断してもらうと良いでしょう。
高血圧
血管にかかる圧力が高い状態が長く続くと、高血圧になります。高血圧が続くと血管にダメージが及び、動脈硬化が進んでしまいます。血圧の基準として、診察室血圧が140/90mmHg以上、家庭血圧が135/85mmHg以上の場合に高血圧と診断されます。
動脈硬化が進と、心筋梗塞などの心疾患や脳梗塞などの脳血管疾患、腎臓病などを発症するリスクが高まってしまいます。高血圧の主な治療方法は、まずは減量を行います。食事習慣をはじめとする運動習慣や睡眠などの生活習慣を改善し、塩分の摂取に気をつけた食生活を心がけます。また、状態によって内服薬を用いて血圧をコントロールすることもあります。
高尿酸血症(痛風)
血中の尿酸値が高い状態が続くと、高尿酸血症となります。血中尿酸値が異常に高くなると、尿酸が血症となって関節に蓄積されます。尿酸を生成するプリン体は、レバーやビール、干しシイタケ、魚卵などに多く含まれています。高尿酸血症の治療は、プリン体の摂取に十分に注意しながら、適度な運動と食事の改善で体重を適正に戻し、肥満を予防します。尿酸値が高い状態を放置すると、痛風という発作が起こり、激しい痛みに襲われることがあるため、なるべく発作を起こさないように薬物療法によってコントロールしていきます。